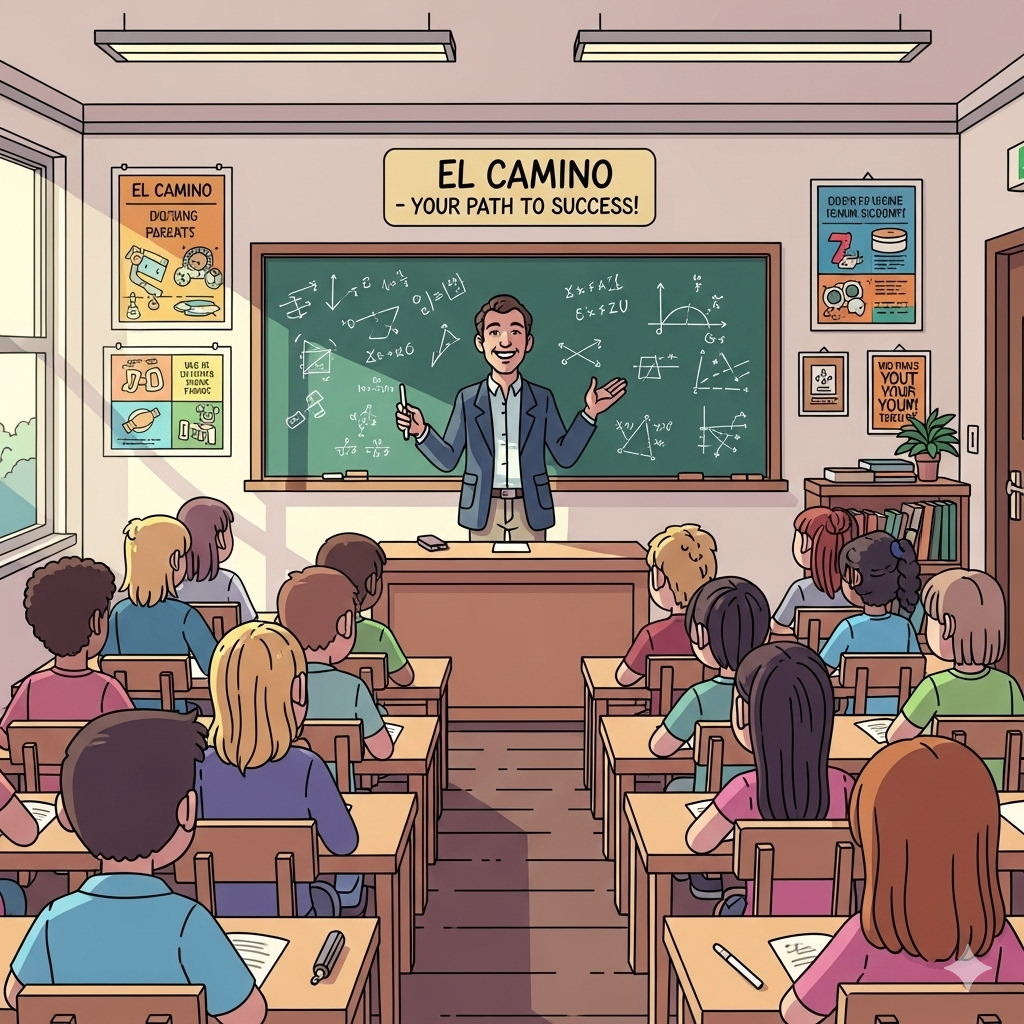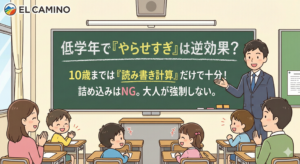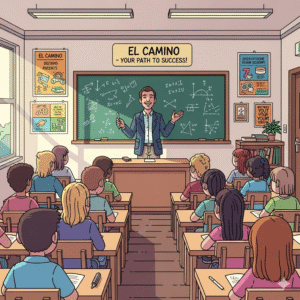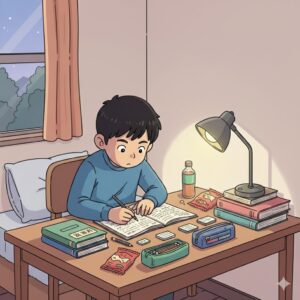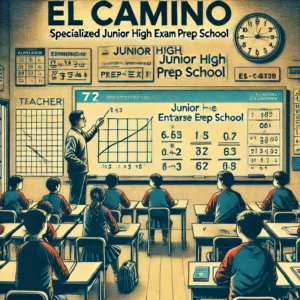いよいよ小4への進級テストが来月となりました。9月の授業はそのための準備です。説明動画の内容から進級テストの内容と対策について解説します。その後、9月の内容についてまとめていきます。
進級テストに向けた説明動画の内容
国語の学習
1. はじめに:学習の全体像と最終目標
進級テスト対策の動画で説明されている学習方法は、9月に行われる進級テストで良い成績を収めることを目指すだけでなく、より重要な目的を持っています。それは、小学5年生、6年生になっても通用する、国語の正しい勉強法を今のうちに確立することです。これは算数の動画でも同じことを言っていました。
2. 家庭学習の具体的な進め方と時間配分
国語の家庭学習は、以下の手順と時間を目安に進めます。
- 学習の流れ
- 音読
- 演習
- 丸付け・直し・意味調べ: 答え合わせをし、分からなかった言葉の意味を調べます。毎回辞書で調べるのが負担の場合、親がスマホで調べて教えてあげるのも可とのことでした。
- 時間の目安:
- 基本問題: 音読 約5分 + 問題演習 約10分
- 応用問題: 音読 約7分 + 問題演習 約15分
- ※この時間で解ききれない場合は、文章を読むスピードがおそいかもしれません。

今までの宿題『新演習』より字が小さいし、文字数も多いね・・・



字が細かくて読むの大変だよ~💦
3. なぜ教材は「難しい」のか?その意図と狙い
国語の教材は小学3年生にとって意図的に難しく作られています。
- 難しさの具体的な要因:
- 一行が長い: 本文のレイアウトがこれまでの『新演習』とはと異なり、一行が長く大人向け書籍のようになっているため、視覚的に難しく感じます。文字も小さいです。
- 単純な「書き抜き」ではない: 「本文中から書き抜きなさい」という指示ではなく、「当てはまる言葉を考えて書きなさい」といった形式が多く、文脈に合わせて言葉を調整する必要があります。
- 応用問題のボリューム: 応用問題は文章量が多く、記述問題も「なぜ〇〇したのかを3行で説明する」など、思考力と表現力が求められます。
- 教材の真の目的:「解説を読む」習慣づけ これらの難しい問題の狙いは、自力で満点を取ることよりも、解いた後に必ず「解説」を熟読することにあります。解説には、問題作成者が「本文のどの部分を根拠として答えを導いたのか」が示されています。これを読み解くことで、国語が得意な人の思考プロセスを追体験し、正しい考え方を学ぶことが最大の目的です。
4. 最も重要な学習姿勢:「本文を根拠に考える」ということ
学年が上がっても国語で伸び悩まないために、最も重要な学習姿勢です。
- 陥りがちな間違い: 「なんとなくこう思ったから」「僕はこう感じたから」という自分の感想や感覚で答えてしまうこと。これは文章が平易な低学年のうちは通用しますが、文章が複雑化・抽象化する5年生以降になると、成績が伸び悩む大きな原因となります。
- 目指すべき姿: 常に「本文のどこに、どう書いてあるから、この答えになる」という根拠を本文の中から見つけ出し、それをもとに解答する習慣を徹底することが求められます。
- 宿題のゴール: 問題を解いて丸付けをするだけで終わらせず、「解説を読み、自分の考えと正解へのアプローチの違いを認識し、反省する」ことまでを1セットの宿題と捉えることが重要です。
5. 保護者のための具体的なサポート方法
子どもが正しい学習法を身につけるため、保護者の関わり方が非常に重要になるとのことでした。
- 記述問題の採点:
- 寛容な姿勢で: 模範解答と一字一句同じでなくても、趣旨や方向性が合っていれば「丸」にしてあげてくださいという説明でした。(例:「将来」を「大人になったら」と書いてもOK)
- より良い表現の提案: 丸をつけた上で、「『どうなるのか』でも良いけど、『どんな仕事に就きたいのか』と書く方が、問題の意図に合っていてもっといいね」というように、アドバイスを添える形が理想です。
- 漢字の形は問わない: 記述の解答中は、内容を考えることに集中させるべきです。握力の発達も途上であるため、漢字の形が多少崩れていても減点せず、まずは内容が合っていることを褒めてあげましょう。
- 言葉の意味調べ:
- 「手持ち無沙汰」「ばつが悪そうに」「きざな台詞」など、大人が思う以上に子どもが知らない言葉は多いものです。「この言葉の意味わかる?」と問いかけ、辞書ではなくスマホで一緒に調べて教えてあげるのも可です。
- 振り返りの伴走:
- 特にお子様が一人で解説を読んでも、本文中の根拠となる箇所を見つけられない場合は、親子で一緒に「解説ではこう言っているけど、本文のどこだろうね?」と探してあげると、学習がスムーズに進みます。
6. 進級テストに向けた漢字練習
漢字練習は点数に直結する重要な分野です。
- 漢字の重要性:
- 配点: テストは200点満点(算国各100点)中、漢字の読み書き5問ずつ計10問が20点を占めます。
- 合格ラインとの関係: 合格ラインは年によりますが、おおよそ120点。これは算国それぞれ60点で到達できる点数です。範囲が決まっている漢字で20点を確保できれば、読解問題は残り80点中40点(つまり半分)の正答で合格ラインに達する計算となり、精神的に非常に有利になります。
- 学習のポイント:
- 出題範囲: テストに出る漢字は、テキストの「漢字練習」のページからのみです。本文中に出てくる漢字は範囲外なので、学習範囲を絞って集中的に取り組みましょう。
- テスト本番の時間配分: 試験時間は30分です。漢字1問を丁寧に書きすぎて時間を消費すると、長文読解に使える時間が25分に減ってしまいます。「読めるレベルの丁寧さで、かつ素早く書く」練習も意識し、配布される模擬試験で本番のペースを掴むことが大切です。「5分は使いすぎ」とのことでした。



9月の対策講座1回のテキストで、当日に読み10問、書き10問、宿題で読み10問、書き10問です。なので合計で読み80問、書き80問の中から、進級テストで読み5問、書き5問が出題されるということになります。これは確実に取りに行きましょう。



小学生で習う漢字1026字なので、このうち80個書けるようになるのはとても良い勉強になります。
算数の学習
1. はじめに:学習の全体像と最終目標
この動画で解説される算数の勉強法は、単に目の前の問題を解けるようにするためだけのものではありません。最終的な目標は、入試本番で初めて見る問題(初見問題)に遭遇したときに、誰も教えてくれない状況でも、自分の力で考え抜き、答えを導き出せる力を養うことです。



まさにエルカミノっていう指導方法ですね。



このやり方が不親切だと思うならエルカミノは向きませんというような言い方を保護者会の動画で毎回のようにされています。
2. 算数学習の鉄則:「×になったら、解説を見ずに解き直す」
家庭学習を進める上で、最も重要で徹底してほしいルールが以下のフローです。
- 問題を解く
- すぐに丸付けをする
- 正解だった場合でも、余裕があれば解説と自分の解き方を比べ、より効率的な方法がないか確認するとさらに力がつきます。
- ×(間違い)だったら、絶対に解説を見ない
- 解説の式や図を見た時点で「種明かし」と同じになり、自分で考える最も重要な機会が失われてしまいます。
- もう一度、最初から自力で解き直す
- 2〜3回解き直しても分からない場合は、①その単元の前の問題を見返す、②授業でやった同じタイプの問題や解説(授業動画)を見返す、という手順でヒントを探します。
- それでも解けない場合に初めて解説を見ますが、そのレベルだと解説を読んでも理解できない可能性が高いため、保護者のサポートが必要になります。
この「解説に頼らず、習ったことを思い出して目の前の問題に応用する」プロセスこそが、入試本番のシミュレーションであり、算数の力を本質的に高めるトレーニングとなります。
3. 計画的な学習スケジュールの重要性
この学習法は時間がかかるため、無計画に進めると終わりません。ご家庭で学習スケジュールを立てることが非常に重要です。
- 宿題は授業の記憶が新しいうちに
- 「授業で習ったことを思い出す」ことが鍵なので、授業があった日の翌日か、遅くとも翌々日までには宿題に取り組みましょう。週末にまとめてやろうとすると、授業内容を忘れてしまい、学習効果が半減します。
- 丸付けもできるだけ早く
- 小学3年生は、間違っていても思い込みで丸をつけてしまうことがよくあります。保護者の方が宿題をやったその日のうちに丸付けをしてあげてください。そうすることで、お子様が解き方を覚えているうちに、効率的に「解き直し」に取り組めます。
- 学習時間の目安
- 「15分問題を解き、15分解き直しをする」といった30分の学習セットを、週に3回程度確保するのが理想です。
4. テキストに隠された「しかけ」
テキストは、子どもたちが自力で考えられるように意図的に作られています。
- 宿題は授業の復習
- 宿題の「演習問題」は、授業で扱った問題の数字を変えただけのものが多く、授業内容をしっかり思い出せば解けるように設計されています。
- 問題の配列がヒントになっている
- 特に図形問題などでは、前の問題が次の問題のヒントになっています。(例:(13)番で補助線が引かれた問題を解かせ、(15)番では似た図形で自力で補助線を引かせる)「さっきの問題と似ているから、同じように解けるかも?」と類推する力を養います。
- 解説はわざと不親切
- 解説には式などが淡々と書かれているだけで、詳しい説明はありません。これは、解けない子へのヒントではなく、自力で解けた子が自分の考え方を確認するためのものです。
5. 保護者のサポートで最も注意すべきこと
お子様の「考える力」を奪わないために、以下の点にご注意ください。
- 安易にヒントや答えを教えない
- 特に図形問題で「ここに補助線を引くんだよ」と教えてしまうと、その問題で最も価値のある「ひらめく」という経験をお子様から奪ってしまいます。それは、一番越えるべきハードルを大人が越えさせてしまう行為です。
- 「応用問題」は必須ではない
- テストの合格ライン(算国合計120点程度)は、「演習問題」レベルがしっかり解ければ十分に超えられます。応用問題は、意欲のある子がさらに挑戦するためのものなので、無理に取り組ませたり、教え込んだりする必要は全くありません。
- 間違いは消さずに残す
- 間違えた解き方は消さずに残しておくことで、「1回目はどこで間違えたのかな?」と後から振り返ることができます。
この学習法は「覚えることより、自分で考えること」が好きな子に向いています。3年生の今は、高学年で宿題が倍になっても保護者の手を借りずに自走できるための大切な準備期間と捉え、焦らずじっくりと「正しい勉強のやり方」を身につけていくことが最も重要です。
テストの全体像
概要
- 科目: 国語と算数の2科目
- 試験時間: 各科目 30分
- 配点: 各科目 100点 (合計200点満点)
- 合格ライン: 例年、合計 120点 程度が目安です。各科目で60点を目指せば、合格ラインに達する計算になります。
国語
国語のテストは、漢字と長文読解の2つのパートに分かれています。
- 漢字 (20点)
- 配点は100点中20点と、非常に重要です。
- 出題範囲は、テキストの「漢字練習」のページからのみです。文章中に出てくる漢字は出題されません。範囲が決まっているため、しっかり対策すれば確実に得点源になります。
- 長文読解 (80点)
- 説明文と物語文の2つの文章が出題されます。
- 問題の難易度は、普段の宿題(家庭学習編)よりも解きやすくなっています。
- 宿題のように記述問題ばかりではなく、「接続詞を選ぶ」といった一般的な選択問題も含まれます。
算数
算数のテストは、テキストの**「演習問題」**が解けるかどうかが合格の鍵を握ります。
- 中心となるレベル (約56点分)
- テストの半分以上(約56点分)は、テキストの「演習問題」レベルの問題で構成されています。そのため、応用問題が解けなくても、演習問題を完璧にマスターしていれば合格点(60点)に大きく近づけます。
- 難しい問題の構成
- 一部、難しい問題も出題されますが、そうした問題も「(1)だけは解ける」ように作られていることが多いです。
- 「応用問題」の扱い
- テキストの「応用問題」は、演習問題がスラスラ解ける子のための挑戦問題です。テストで合格点を取るために解ける必要はありません。
まとめ
合格への戦略は、国語では範囲の決まっている漢字20点を確実に取ること、そして算数ではテキストの「演習問題」を完璧に解きこなせるようにすることが最も重要です。
次の記事では実際に9月の1か月間でどのような内容が授業で扱われ、家庭学習をどうしていったかを解説していきます。↓↓↓